
脳髄はものを思うにはあらず 「知能はどこから生まれるのか」大須賀公一 を読む
ゴリゴリの制御工学者であった筆者が抱いた問い。それは知能の源泉とは何なのか、と言うもの。その問いを探るために筆者はムカデ型ロボットを作り、構成論的アプローチからその問いに迫る。そしてその武器は、哲学者フッサールが提唱した、「現象学」である。
生成AI×プロダクトマネージャー(PdM)×中小企業診断士。X(旧Twitter)は@KovaPlus

ゴリゴリの制御工学者であった筆者が抱いた問い。それは知能の源泉とは何なのか、と言うもの。その問いを探るために筆者はムカデ型ロボットを作り、構成論的アプローチからその問いに迫る。そしてその武器は、哲学者フッサールが提唱した、「現象学」である。

「本を読む本」は読書論の古典ともいえる名著だ。その中で紹介されている読書法、点検読書とは、いわば「系統立てた拾い読み」のようなもので、一冊の本がどのような本であるか、短時間で効率よく性格に把握するための読書法だ。

「本を読む本」は、「読むに値する良書を知的かつ積極的に読むための規則」について述べた本である。 キーワードは「積極的読書」。良く整理・体系化された名著であり、読書家を自認するならぜひ読んでおくべき一冊。
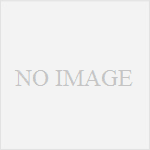
「読書百遍義自ずから見る」はじめは理解できない文献でも百回読めば意味が理解できてくるという言葉だが、本当に効果はあるのか。短期大学にて学生たちを対象にして実地調査を行った研究論文を読んでみた。結果は効果はある、ということだが。。。

外国語や学習塾、スポーツなどどんな習い事よりも優先して子供に身につけさせたいスキル。それが読書である。文字を早く読み、その内容を正確に理解することは、日常のあらゆる場面で有利に働く何よりも重要なスキルである。