 書評
書評 タコの知性を知り、人間の心を知る:タコの心身問題 書評
哲学者である著者がタコの生態の観察を通じて、単なる物質である我々にどのようにして知性や心が生まれたのかを探る一冊。タコやイカ等の頭足類が主たる題材ではあるが、そのテーマは頭足類を一つのモデルとして、生物や人間の心の在り方を問う挑戦的な内容だ...
 書評
書評 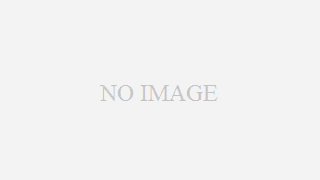 書評
書評 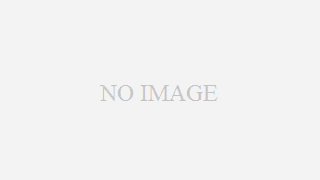 書評
書評  書評
書評 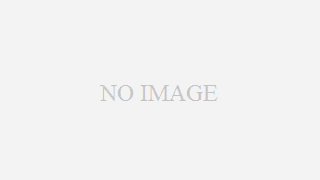 仕事の話:PdM奮闘記
仕事の話:PdM奮闘記 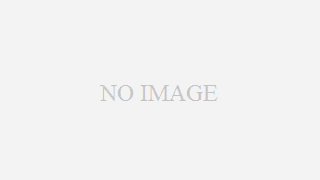 書評
書評