ビジネスマネジャー検定合格を受けて
2020年から管理職(課長職)を引き受けることになりました。が、社内では管理職むけの教育プログラムなどは皆無です。また、正直なところ社内をみても手本となりそうな管理職がいません。そこで世間一般レベルの管理職として基本的素養を身につけるため、東京都商工会議所の「ビジネスマネジャー検定」を探し出して受験し、苦労の末合格しました。(詳細は下記の記事)
はて、ここで一通りマネジメントに関する一般的な基礎知識を学んだわけですが、意外と自分自身の興味や適性が企業の経営・管理の部分に向いているのではないか、ということに気づきました。技術分野を掘り下げるよりも、管理分野の方が面白そうと感じたのです。
管理の実践については日々の職務の中で行うことができ、それで能力を磨いていくことができます。一方で知識・理論武装もして行きたいと思いました。そこで次のステップアップとして考えられるのは「MBA:経営学修士号」と「中小企業診断士」です。MBAについては自分の出身大学で社会人向けの講座があることは知りましたが、通う時間を捻出するのは難しそうなので却下。一方、中小企業診断士については、かなりの難関試験になりますが独学でも勉強していけそうなのでこれを目指すことにしました。また2次試験合格後に一般企業に派遣されて実務を行う必要がある(機会がある)ということも魅力的に感じました。
さらにその背中を後押ししたのが、ビジネスマネジャー検定試験時に参考にした中小企業診断士のテキストの中にあった、「中小企業診断士の受験者は製造業の現場をテーマにした「生産・技術」分野を苦手にすることが多い」という記述でした。
この理由の一つとして考えられるのは中小企業診断士受験者のバックボーンの偏りです。すなわち、おそらく受験者は文系出身者が多く、製造業出身で現場を知るものがあまり受験していないということ。これは技術者である自分が中小企業診断士に合格した暁には、技術者出身であることが診断士として差別化する要因になるということ。また技術者として生きていくにしても、比較的少数の組み合わせである「技術者×中小企業診断士」が希少価値になるのではないか、という期待が自分の中に生じました。
ということで目標は中小企業診断士合格、頑張って行きましょう。
テキストを購入
まず、独学用にテキストを買います。ビジネスマネジャー検定のときにも参考にした簡単なテキストが下記。
しかしこれだけでは到底内容が足りないので、LECの教科書を買いました。2冊合わせて¥8,000くらいしますが、頑張って買います。
とりあえず上巻から勉強をはじめました。やはりこの分野は水が合うのか、勉強していても結構楽しいです。この気持ちがどこまで続くかですが。。。
勉強計画 2カ年で
中小企業診断士は1次試験と2次試験の2回試験をパスする必要があります。まずは次回2021年の8月の1次試験がターゲット。年末年始はまとまった時間が取れると思うので、ここで過去問をひたすら解いて行きます。なのでそれまでに一通りテキストを読みます。早めのタイミングで過去問を解いて、出題内容を把握したいのでもしテキストの進捗が遅くとも年末には過去問を解き始めます。
過去問解いてどれぐらい解けるか確認後、2021年からの勉強計画を調整していこうと思います。
次回のブログは年末に進捗状況でも書きますかね。



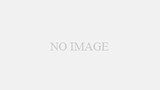
コメント