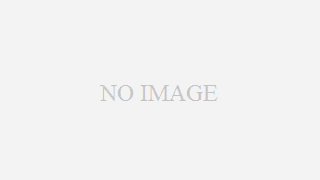 書評
書評 スタニスワフ・レムの「砂漠の惑星」は人間の視点を相対化させる
人間のエゴ:”地球が”泣いている「砂漠の惑星」は「ソラリス」で有名なスタニスワフレムが書いたSF小説である。(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b=b||function(...
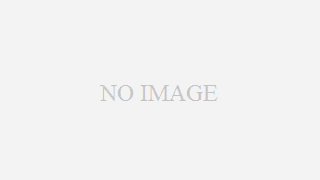 書評
書評 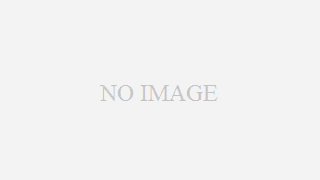 書評
書評 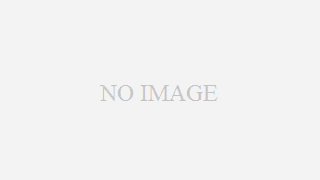 書評
書評 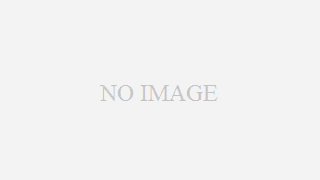 書評
書評